
茶飲み話・正露丸
私の子供の頃に飲んだ薬の中で、いちばん印象に残る薬はなんといっても、あの強烈に苦い「正露丸」である。黒くて長丸だった正露丸はわが家の常備薬ではなく、たまたま訪れた友人宅で飲んだ記憶がある。その時は別に腹痛でもなく「これ噛んでみ」とふざけ半分に手渡された。まだ昭和も30年前後なのでクスリの多くが漢方などの生薬だった。
当時わが家では風邪をひくと「改元」という顆粒で同じくほろ苦い生薬を飲む。そして厚い布団を頭からかぶり、顔を真っ赤にして汗をかく。すると熱も下がり、2,3日で全快した。しかしこの方法は子供の体力が落ち、健康によくないとかで徐々にすたれていった。すると同時に改元もクスリ箱から消え、「ルル」や「パブロン」といった大手製薬会社などの西洋薬に代わった。
「パブロン・ゴールドがいま急激に売れている!」その原因はまた始まった中国人によるクスリの買占めであるという。ゼロコロナ政策での都市封鎖をいきなり解除したお隣では、いま感染爆発がすさまじい勢いだ!そのため患者であふれる病院はまともに機能せず、多くの人々は薬局で売る薬に殺到する。結果品薄になった風邪薬は5,6倍に跳ね上がった。
そしてこれを商機と考える中国人が、日本やアジア各国で風邪薬の買占めに走る。中には在庫全部、あるいはダンボールごと買う人もいて日本でも風邪薬が品薄になる可能性もある。特に中国人に人気の大正製薬のパブロン・ゴールドは、飲むとじきに症状が和らぐので特に人気があるらしい。数年前のマスクと同様に今回もマツキヨの棚から風邪薬が消えて、定価では買えない事態など起こらなければよい。
「良薬は口に苦し」という格言が昔あった。今のクスリはまわりがコーティングされているので、クスリの味を感ずることは殆ど無い。でもクスリが苦いとなんとなく効く感じもする。コロナの出始めでは正露丸が効くのでは?という冗談めいた話も聞いた。(もうすぐ中国の春節が近づく、でもコロナ禍での来日は控えて欲しい。勝田陶人舎・冨岡伸一)
年賀状

茶飲み話・年賀状
「あけまして、おめでとう御座います。今年もブログのフォローなどよろしくお願いします」。ところで新年といえば元旦に届く年賀状は楽しみの一つであるが、せんじつ旧友の一人から「そろそろ互いに年賀状のやりを取り終了しないか」との提案があった。実は私も同じことを考えていたので、「渡りに船」とばかりに快諾した。
わが家では年賀状は毎年下絵を私が考え、妻がそれを版画に掘ってもう40年以上続けた。でも歳を重ねるとその作業が徐々に負担になり、今年で終了することにする。定職を持つ身ではないので、師走といえどさして忙しいわけではないが、年賀状書きがなくなれば気分的にはだいぶ楽になる。しかし年賀状のやりとりは長年会ってない学生時代の友などもいるので、安否確認にはよい点もあった。
最近は「年賀状の代わりにラインで送ればよいよね」とすでに若い人からどんどん年賀状離れが進み、SNSでのやりとりに代わった。それが徐々に熟年世代と伝播し、もう数年すると年賀状という慣習も激減すると想う。かつては年賀状の枚数で交友関係の広さを競ったが、もうそれも過去の思い出となりつつある。
先日「ピンポン!」とラインメールの着信音でうたた寝からさめた。見ると親友からの動画だ。アイコンをスクロールし、現れた美しいクリスマスツリーの写真をタップする。すると私の好きな山下達郎の「クリスマス・イブ」のメロディと共に、素敵な映像とメッセージが流れる。その日はちょうどクリスマスイブだった。カードの代わりに動画とは時代の変化を痛感する。
いま世界の人口は80億人をこえる。日本は人口減少だが後進国では人口増が止まらない。そこで人類一部は宇宙に進出するか、メタバース仮想空間にこもるかの二択になる。2045年にコンピューターAIが人類の思考を超えるシンギュラリテーがくるといわれていたが、2025年に早まったという。いったい人類の未来は明るいのか?戸惑うばかりである。(今年もまた激動の一年が始まった。勝田陶人舎・冨岡伸一)
80歳の壁

茶飲み話・80歳の壁
最近、昔よく通った駅近の本屋に出かけてみると入り口の脇に、老後生活をいかに過ごすかの様々な指南書がワンコーナー、ビッシリと並べられていた。そういえば工房のある八千代市勝田台団地も多くの住民が高齢者となっており、団地内を巡る循環バスに乗ると、およそ八割がシルバー世代で座席をうめる。あと10年もすると世代交代がスムーズに行なわれないと、この街は空き家だらけになる。
今年の年間ベッストセラー総合第一位は、医師の和田秀樹さんが書いた「80歳の壁」である。この内容を要約すると80歳を超えたら無理をせず、勝手気ままに好きなことをして自由に生きる事だそうだ。そのほか吉村芳弘医師の書いた「80歳の壁を超える食事術」という本も話題になっている。その副題は70歳になったらしっかり食べて、しっかり太っておきまあしょう!とある。
なにしろ80歳をむかえたら不必要なダイエットなどをせず、カロリーの高い肉なども多く食べ、小太りぎみな身体にしとくことが長寿の鍵となるらしい。でもウェストまわりがタイトで穿けなくなった多くのズボンを眺めると、もう少し痩せたいの願望がよぎる。しかしこの歳になると多少の節食では体重は減らない。そして1キロ痩せるのにも長い時間をかけることになる。
「あなたも泳いだら」。とフランス人ガールフレンドのベルナデットに促がされたことがある。それは半世紀以上もまえの、パリから北西部にあるドーバー海峡に面した遠浅の砂浜が続く海水浴場である。6月の海辺は太陽がまぶしく、目を細めて陽光をさえぎっていた。「うん、私はいいよ」とかるく首を横にふった。実はこの日、彼女の従兄弟数人がはるばる日本からやって来た私を、車で海水浴に誘ってくれたのだ。浜に着くと彼らは一斉にシャツを脱ぎ捨て、水辺までて走って行った。
今では身長170センチ、体重68キロの私も青春時代は体重53キロで痩せていた。日本では海水浴に行っても自分がやせていることにあまり意識が無かったが、フランス人男性は上半身筋骨隆々でよい体格をしている。それに圧倒され、とても裸になれない自分がいた。「こんなことならもっと身体鍛えておけばよかった」とコンプレックスを強く感じその場をにごした・・・。(本年もフォローありがとうございました。良いお年をお迎えください。勝田陶人舎・冨岡伸一)
ロボホン
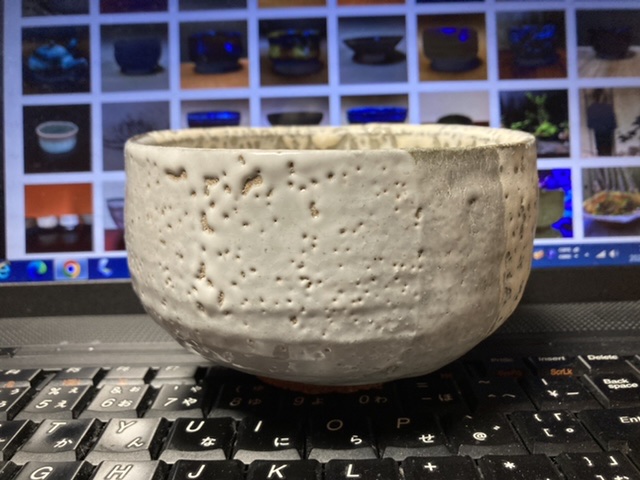
茶飲み話・ロボホン
「ロボットと楽しく会話」という記事が先日読売新聞に掲載されていた。最近コミュニケーションロボットが進化し人の話し相手になったり、ダンスを踊ったりするらしい。とくにシャープが開発した20センチぐらい大きさのロボット「ロボホン」が売れているという。価格は13万円代でペットのように愛玩し、服まで着せるというので驚きだ。
独り世帯が急増するこれからの時代、話し相手なると同時に自身の健康状態などもチェックし、緊急の場合は行政などにも通報してくれるスマートロボットなどあれば嬉しい。世帯主との日常会話を通じて、データー管理し認知症など初期症状の発見も人間よりも的確に行なえると想う。
これは数年後の話だが、ある朝「おはようございます。ご気分はいかがですか?」とロボちゃんの声。彼女の目を見つめると「今朝は血圧が高めなので、すぐにお薬飲んでください」と支持がきた。そこでゆっくりとシンクに向かい蛇口をひねり、カップに水を注ぎ薬を飲み干す。「なんかニュースある?」の私の問いに「中国が台湾に侵攻しました」と答えた。「それはえらいことだね」と返す。
テレビや新聞もあまり見くなった私は好きだったユーチューブさえ検索しない。でも必要な情報はすべてロボちゃんが精査し、その都度教えてくれるのだ!とまあこんな状態になっている。時代のトレンドについて行くかどうかは個々人の勝手だが、ミーハー感覚で時代を楽しむのも悪くない。なにしろ寿命が百歳オーバーになるのでまだ先は長い。
仮想空間メタバースの中でセクハラの横行!臨場感があり「とにかく気持ち悪い」というニュースもある。俺の知らぬ間にもう時代はそこまできているのか?「いいじゃん、お互いアバター(化身)なのだからお尻ぐらい触っても」。仮想空間の中でも法律やルールが必要なようです。(現実世界ではロボットとの共存、仮想空間ではアバター。凄い時代になる。勝田陶人舎・冨岡伸一)
神隠し

茶飲み話・神隠し
政府は航空自衛隊の名称を「航空宇宙自衛隊」に変更することを決めた。安全保障の領域でも宇宙の重要性が高まり改名に踏み切ったらしい。今中国は独自で宇宙ステーションを建設し、それを軍事基地化するためにいろいろな実験や、新しい武器開発を急いでいる。この基地からレーザー照射すれば敵のミサイルなど、いとも簡単に打ち落とせるそうだ。
「まことに恐ろしい時代になった!」現在でも宇宙ではたくさんの人口衛星が飛び交い、日々われわれの日常を監視する。すでに道を歩く個人さえ特定できるレベルにカメラ性能も向上しているので、狙われたら最後この罠からは逃れることができない。たぶん北朝鮮のデブ坊やなどの行動は、アメリカによりある程度把握されていると想う。
この機能とレーザー光を組み合わせれば、個人など意とも簡単に消し去る事ができるらしい。道を歩いていた個人がある日突然いなくなった!ただその場所には黒く焼け焦げた痕跡があるだけなんてことも。この技術が確立すれば共産党習近平の政敵など皆な消される!「こいつウザイ奴だ!」とパソコンのデリートキーをタップする。すると瞬間に人、一人が削除された。
私の地元市川市八幡には不知森という藪があった。この藪に一度足を踏み入れると二度と出てこられないという伝承がある。江戸時代でもさほど広くないこの藪に入るとなぜ人が消えるのか?たぶん天狗などの仕業による「神隠し」ではないかと言われていた。水戸黄門がこの話を聞きつけ、ばかげた話だと当地に立ち入ったところ、白髪の老人が出てきて掟を破るなといわれたとか?
現在でも人が突然いなくなることがままある。そこで原因不明時に、いまでも人はこれを神隠しと呼ぶ。でもこれからは重要人物の神隠しなど、横行するかもね?真上から突然攻撃されたら防御のしようもない。将来は宇宙から監視されない地下都市に住むのがはやるかも・・・。テクノロジーの進化もよいが功罪相半ばする。(写真。八幡の藪知らずの跡地神社です。勝田陶人舎・冨岡伸一)
